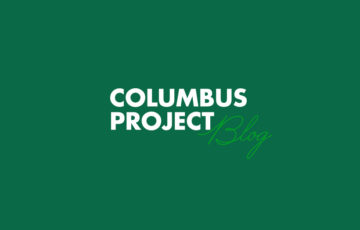大企業でも、中小企業でも、新規事業や新サービスに対して、「それはできないよー」「無理無理、やめたほうがよい」など、否定的なことを言う人がいます。
ある意味正しいし、ある意味間違っていると思うのですが、そんな話を聞いていたときに、「イノベーション」という言葉が思い浮かびました。
「イノベーション」という言葉は私の身近なところではアップルのiPhoneの発売と爆発的なヒットによってよく使われるようになったと思います。
イノベーションとは
イノベーション(英: innovation)とは、物事の「新結合」「新機軸」「新しい切り口」「新しい捉え方」「新しい活用法」(を創造する行為)のこと。一般には新しい技術の発明を指すと誤解されているが、それだけでなく新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し、社会的に大きな変化をもたらす自発的な人・組織・社会の幅広い変革を意味する。つまり、それまでのモノ・仕組みなどに対して全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出して社会的に大きな変化を起こすことを指す。
イノベーションは、1911年に、オーストリア出身の経済学者であるヨーゼフ・シュンペーター[2]によって、初めて定義された。
シュンペーターはイノベーションを、経済活動の中で生産手段や資源、労働力などをそれまでとは異なる仕方で新結合することと定義した[3]。そしてイノベーションのタイプとして、
新しい財貨すなわち消費者の間でまだ知られていない財貨、あるいは新しい品質の財貨の生産
新しい生産方法の導入
新しい販路の開拓
原料あるいは半製品の新しい供給源の獲得
新しい組織の実現
という5つを挙げている。
イノベーションはしばしば次の2つに分類される[4]。
プロダクトイノベーション(製品革新): 新製品の開発によって差別化を実現し競争優位を達成するイノベーション
プロセスイノベーション(工程革新・製法革新): 製造方法や工程の改良によって費用を削減し競争優位を達成するイノベーション
ただし、どちらも経済学的には生産関数の上方へのシフトで表され、これらの区別は決定的なものではない(ただし、後者は全要素生産性によってあらわされるとされる)。
wikipediaに書いてある「イノベーション」の中でも重要なワードは
価値を創造
新結合
5つのタイプ
差別化
の4つだと思います。
新たな価値の創造
価値の創造というのは、本当に身近な範囲で体験できますし、常に生み出すことができます。もちろん組織単位であったり大きく新しい価値の創造は難易度が高いですが、でも一つ一つの積み重ねです。価値創造をこつこつ生み出していけば大きな価値につながります。個人でできる価値創造がまず第一歩。
組織で価値創造を行う場合は、組織の価値と創造する価値を個々人が見直す必要があります。トップダウンでも組織に浸透すれば問題ありませんが、浸透する前に価値が弱まる(トップがつかれる、現場がアウトプットできない)ことも多いので合意形成型で組織と個人が価値をはっきりさせておくことがおススメです。
この新たな価値の創造は、今の自分たちを置いておいて本質的な価値を見定めることが大事です。
・1日かかっていたことが1時間でできるようになった。涙が出るほどありがたい。
・今まで100万円かけていたものが、10万円でできるようになった。10万円で10回行えることのほうがありがたい。
・面倒くさがりやなのでちょっとの手間がなくなることがとてもうれしい。
・PCを立ち上げずにスマホですぐにできる。なんだか私ができる人になったみたい。
本質的な価値は、ちょっとした欲求や課題の解決が積み重なってできあがるので日頃の身の回りの価値発見、課題発見がとても重要ですね。
新結合
iPhoneでさえ、既存技術の組み合わせと言われますが、事実半分はそうです。アップルの場合、コンセプトや思想が素晴らしい。既存技術と製品コンセプトでイノベーションを起こしていると感じます。
アップルほどではないにしても、既存の技術、スキル、仕組みを組み合わせて、新結合して新しい価値を生み出す、ことは誰しもできることです。
実は仕事を行う中、生活をする中で、日々新結合も行っています。
・今日の夕飯どうしようかな。あ、あれとあれを組み合わせてみようかな。※これも新結合。
・あー、面倒だな、この二つを一緒にやってしまおう。
・Dropboxやオンラインストレージを使えばこのやりとりが簡単にできるな。
・作業を分けて行っていたけど、同時にやれる方法が見つかった。
※逆に、一緒に行っていたけど、分けて行った方が早い。
特に最近は、自分の3m以内にスマホというほぼ24時間世界とつながっているツールがあるため、工夫して新しい手法を取り入れて個人もプロセスイノベーションを日々行っています。
この日々の小さなプロセスイノベーションを一つにまとめることも、大変大きなプロセスイノベーションにつなげられます。
5つのタイプ
この5つのタイプのうち、身近なものとしては
・新しい生産方法の導入
・新しい販路の開拓
この2つがあるのではないでしょうか。
ビジネスマンは誰しも何かしらを生産しています。業務を遂行する、というのも資料を作ったり、モノを作ったり、しています。
またビジネスマンは誰しもお客さんとつながっています。組織の一人であっても組織単位でお客様とつながります。その流通や販売の流れを作る。
これらはともにインターネットやIT、スマホと新しく結合することで新たな価値を生み出せます。
差別化
この差別化が一番の肝なのですが、いわば今の時代は
・インターネットやITやスマホを使って
・既存の仕組みと結合させて
・新たな価値を創造する
ということは簡単にできる時代です。
この3つを行えば、個人レベルであれば簡単に実行でき食べられる時代になったと思います。
逆に言えば、「同じようなイノベーションが生まれやすい」わけです。参入障壁が低くなったともいえると思います。
そんな中で勝ち抜いていくには、どこで「差別化」をするか。この差別化のポイントは最も重要です。
この差別化ポイントは説明しようがありません。ただし、差別化ポイントをこれにしよう!と決めたら下手でも苦手でも取り組んでいくことです。1年間一つのことに取り組むと、実は他との違いになります。おのずと差別化ポイントになります。
組織でのイノベーション文化の醸成
組織がイノベーションや新しい取組に否定的な場合、「小さなイノベ」をお互い発見したり、ほめたりする習慣を作るととても効果的です。
1「付箋に小さな課題を書く」(自分の課題とお客さんの課題の2つの視点から)
2「週に1回の会議で課題を出し合う」
3「課題の中で一つ、みんなで解決する課題を決める」
4「1週間取り組む」
5「次の週次会議で課題解決の取り組みを出し合う」
4~5の繰り返し
小さなイノベーションを生み出すことを繰り返していくと、組織の中で「変化する」「変革する」習慣がついていきます。
そこから組織イノベーションは始まっていきます。小さく始めて大きく伸ばす。
まずはここからスタートですね。
最後にヒトモノカネ
今まで言っていませんが、イノベーションにはヒトモノカネは変わらず必要です。これらの資産が大きく使える環境であるかどうかは大切ですね。
しかしすべて使える環境はまれです。ヒトがいない、モノもない、カネもない。
組織においてはヒトが財産です。モノもカネも少なくても組織にはヒトがある。これを最大限使わずにイノベーションはできません。
だからこそ日々の組織の習慣に「小さな変革」の仕組みを入れることが非常に大きな価値があります。
本当に裸一貫で一人で何かを始めることと比較したら組織に属している人は恵まれていると思います。
「できない」を言わずに、チャレンジとイノベーションに積極的に自然体で取り組みたいですね。
ジョブズと言えば、この本もヒットしましたね。もうジョブズ亡くなったのが2011年10月5日。3年半です。早いですね。